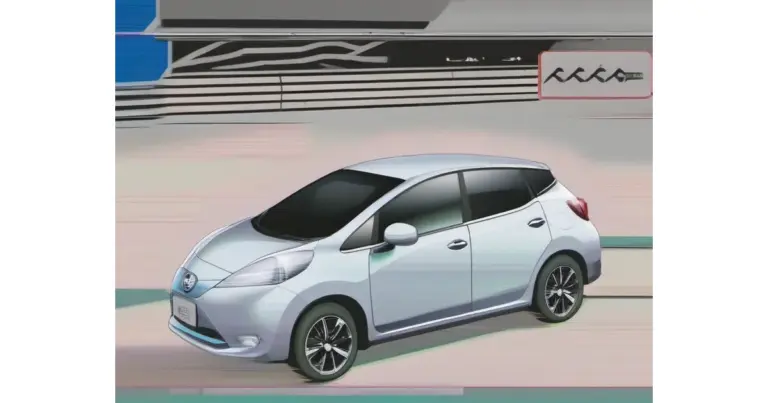主要発行体と発行額の概要と戦略|NISA Labで確認できる最新国内グリーンボンド発
※本記事は複数のRSSから抽出したトピックをもとにAIで要約・構成しています。内容の真偽や最新情報は、下記の参考リンク先(一次情報)をご確認ください。
- NISA Labで確認できる最新国内グリーンボンド発行リストの概要
- 発行リストの更新日と対象銘柄数
- 主要発行体と発行額の概要
- グリーンボンド投資のメリットとNISA枠での活用ポイント
- 税制優遇とリスクヘッジの効果
NISA Labで確認できる最新国内グリーンボンド発行リストの概要

NISA Labでは、国内で発行されたグリーンボンドのリストを閲覧できるようになりました。これは金融庁が公表しているNISA口座利用状況調査資料に基づき、利用者が投資対象を確認できるよう整備されたものです。現状、具体的な発行額や新規発行スケジュールの詳細は資料に記載されていないため、投資判断の際はNISA Lab上で最新データを直接確認する必要があります。現時点では詳細未公表となります。
発行リストの更新日と対象銘柄数

発行リストは令和7年9月25日に更新され、国債に関する最新の発行額が発表されました。特に、10月から12月の物価連動債は、10月と12月にそれぞれ約200億円、11月に未公表億円の入札予定が示され、合計約600億円の発行が見込まれています。流動性供給入札では、残存期間に応じて2年、5年、15年といった複数のシリーズが予定され、総額は未公表億円に上ります。なお、実際に発行される銘柄数や詳細な番号は現時点では未公表です。投資家は最新情報を定期的に確認し、ポートフォリオのリスク管理を行うことが重要です。
主要発行体と発行額の概要
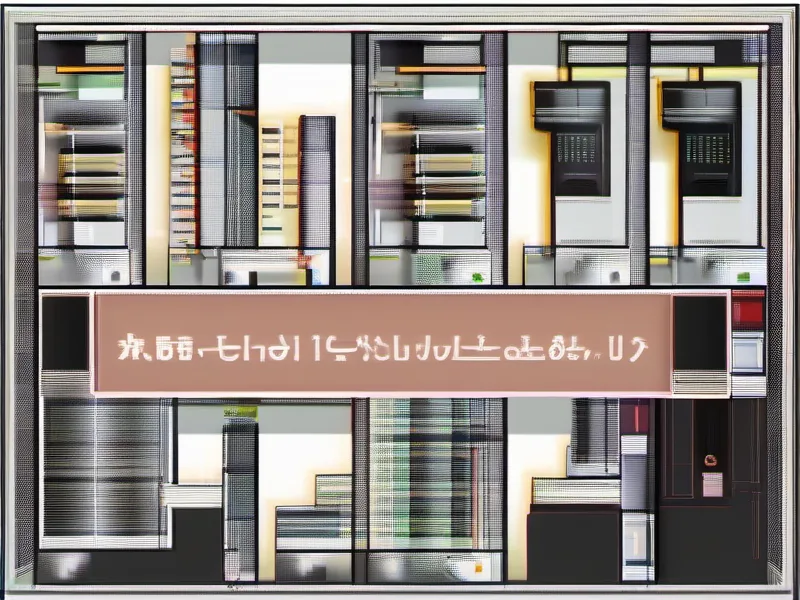
国内のサステナビリティ・リンク・ボンドは2020年に初めて発行され、2025年8月8日時点で多くの企業・金融機関が資金調達を行っている。発行額は環境省のデータベースにより集計されているが、これは発行体自身のラベル申告を基にしており、政府によるスクリーニングは行われていないため、実際の発行規模は報告数より小さい可能性がある。世界市場では2019年から発行が始まり、ICMAが2020年に原則を策定したことで急速に増加している。主な発行体は大手企業や公的機関で、発行額は米ドル換算でOanda社の為替レートを用いて計算されている。現時点では国内発行額の詳細数値は未公表であるが、国際的なトレンドを鑑みると、発行規模は今後拡大する見込みである。投資家は各発行体の開示情報を詳細に確認し、ラベルの自己申告に留意した上で投資判断を行うことが重要である。
グリーンボンド投資のメリットとNISA枠での活用ポイント
国内のグリーンボンド発行リストが更新され、2014年以降の主要発行事例が網羅された。JPXのESG債情報プラットフォームで確認できるデータは、発行体が申告したラベリングをもとに集計されており、環境省による内容精査は行われていない点に留意が必要である。NISA枠を活用すると、グリーンボンドの利息や売却益が非課税になるため、ESG投資を目的としたポートフォリオに組み込みやすい。税優遇は年間未公表までで、同枠内で複数のグリーンボンドを保有できるため、分散投資効果が期待できる。ただし、第三者評価機関の格付けや資金使途の透明性は、個別に確認する必要がある。現時点では詳細未公表のケースもあるため、最新情報を定期的にチェックしながら、税制メリットとリスク管理を両立させる投資戦略が有効である。
税制優遇とリスクヘッジの効果
2025年9月に発行リスト(国内)に追加されたグリーンボンドは、環境関連の投資を促進するために税制優遇が設けられ、所得税の減免や資産運用税の優遇措置が適用されます。この優遇は投資家にとってリターンを増大させ、同時に企業側の資金調達コストを低減する効果があります。さらに、為替ヘッジ付きETFやヘッジ付き投資信託の取扱開始により、外貨建て資産の為替リスクを軽減できるため、ポートフォリオ全体のボラティリティが低下します。結果として、グリーンボンドとヘッジファンドの組み合わせは、税優遇とリスクヘッジの両面から投資家にとって魅力的な選択肢となります。現時点では詳細未公表の点もありますが、上場予定のETFの基準値は参考情報として有効です。